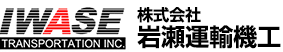月別アーカイブ: 2018年1月
ドライバー防災対策

皆さんは、どのような防災対策を行っていますか?
ご自宅での対策も大切ですが、トラックドライバーの方はお仕事としてもより対策が必要ですよね。
トラックドライバーの方は日本の物流の要です。
是非、お仕事もプライベートも、防災対策を行ってくださいね。
大地震が発生した際は、一人ひとりが周囲の状況に応じて「身の安全をはかる迅速な判断と行動被害を最小限にくいとめ、二次災害を防ぐ適切な処置」が求められます。
また、被災者に対して「迅速・確実に救援物資を届ける」ことは、トラック運送事業者の社会的使命といえます。
災害には、不断の用意が大切です。いざというときに備えてください。
防災対策担当者として
災害は「いつ、どこで、どのような規模」で発生するか予測がつきません。
災害発生に備えて日頃から事業所での防災対策を講じておきましょう。
1、事業所内外の点検と補強
事業所内外の危険箇所の点検を行い、補強する箇所があれば早急に補強します。
什器・備品なども耐震性の強化をはかっておきましょう。
2、職場内での役割分担を
災害時の行動について、火元の点検者、応急救護班など社員に役割分担をさせ、災害発生時に「どのような行動をとるか」明確にしておきましょう。
3、災害時のマニュアル作成を
災害時の行動や役割分担などについて、事業所ごとにマニュアル(行動指針)にまとめておきましょう。
東京都をはじめ、都道府県の多くでは「防災のしおり」などの小冊子を発行しています。入手のうえ、参考にしましょう。
4、緊急・救援輸送の出動に備えて
災害が発生したら、トラック運送事業者は地方公共団体(以下、都道府県等)などの要請を受けて緊急・救援輸送に出動します。
被災者に対して、迅速・確実に物資を届けることは、トラック運送事業者の社会的な使命です。
緊急・救援輸送の出動要請に備えて、出動時に携帯する必需品を準備しておきましょう。
5、非常食の備えを
社員が2〜3日生活できる量の非常食と飲料水を備えておきましょう。
[非常食]レトルト食品、缶詰のご飯、肉・魚の缶詰、カンパン、梅干、チーズなど。
[飲料水]1人1日 3ℓ×3日分(長期保存可能な水)
6、防災訓練への参加
9月1日の防災の日や防災週間(8/30〜9/5)中に、各地で防災訓練が行われます。
トラック運送事業者も町会等が主催する防災訓練には積極的に参加し、いざというときの協力体制を作っておきましょう。
事業所内外の防災ポイント
災害(とくに地震)に備えて、耐震性の強化など事業所内外の防災対策を講じておきましょう。
[危険箇所の点検と補強]
(1)事業所内外の耐震性の強化
災害発生時に怪我をしないよう、事業所のガラスや壁、ロッカー、書庫、倉庫・保管庫のラックなど耐震性の強化に努めておきましょう。
(2)外壁やブロック塀などの補強
建物の外壁や看板、ブロック塀などが落下、転倒する恐れがないかをチェックし、必要に応じて早急に補強しましょう。
(3)荷くずれ防止対策の徹底
倉庫や保管庫では、地震が起きたとき荷くずれが防げるよう、常に荷物の整理・整頓を徹底しておきましょう。
(4)危険物の転倒防止
発火性の薬品や燃料などの危険物は、災害時に備え、転倒・落下防止措置を講じておきましょう。
(5)消火器の準備
地震発生後の二次災害(火災発生)に備え、消火器や三角バケツなどを保有、目につきやすい場所に設置しておきましょう。
(6)避難路の確保
避難する通路や階段には、大きな荷物や危険物などを置かないようにしましょう。
また、避難場所も確認しておきましょう。
(7)地質を知る
地震被害は、地盤の弱い地域および活断層の上などに集中しています。
事業所の地層はどんなものかを知り、そのうえで地震対策を立てましょう。
知っている、ということは強みになります。
知識があれば事前に備えておくことができます。
防災対策は、事前準備が大切です。
さまざまな情報を確認しておくようにしましょう。
引用参考:改訂版 防災手帳~災害に備えて~